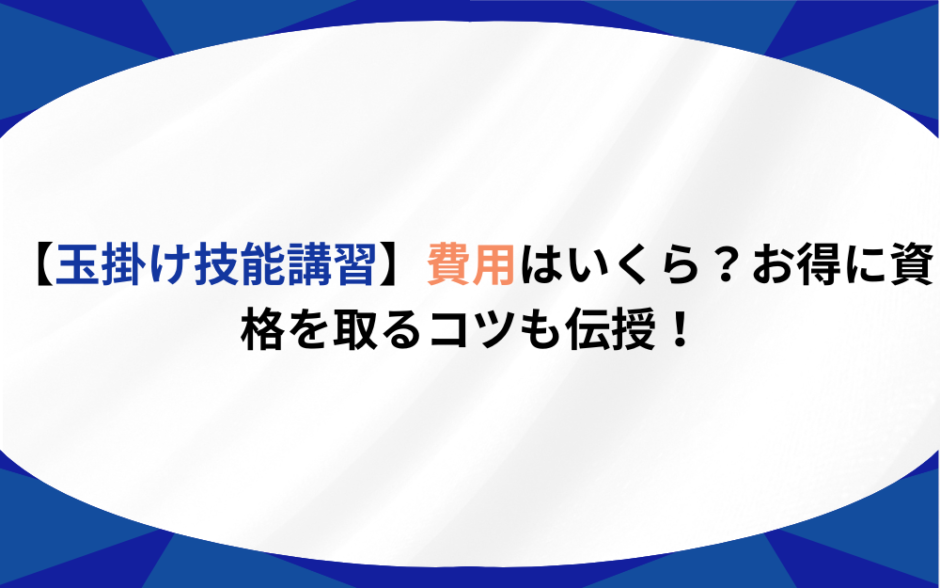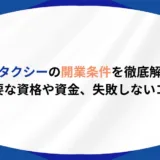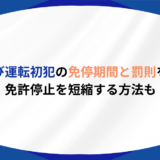この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
クレーンを使った玉掛け作業には、国家資格である玉掛け技能講習の修了が必須です。この記事では、玉掛け技能講習の内容や必要性、費用、試験対策などについて詳しく解説します。資格取得を目指す方はぜひご一読ください。
・玉掛け技能講習とは何か、なぜ必要なのか
・講習の内容と料金相場
・試験の出題範囲と合格のコツ
・申込方法と講習までの流れ
・玉掛けの仕事に向いている人の特徴
【就職・転職をお考えの方へ】
こんなお悩みありませんか?
- もっと給料を上げたい
- 残業時間が多くて体力的にきつい
- ホワイト企業に転職したい
- もっとプライベートを充実させたい
プロドラ編集部が最もおススメする、ホワイト企業で高年収を目指したい人に"絶対"に利用して欲しいドライバー専門転職サイト!
ドラEVERでしか取り扱いのない好条件の求人が多く、年収アップも目指せます!未経験歓迎の求人も多数あるので、異業種からの転職にもおススメ!
そもそも玉掛け技能講習とは?作業内容や対象者を解説

クレーンでの玉掛け作業に必要な国家資格
玉掛け技能講習は、クレーンなどを使って重量物を吊り上げたり移動させる「玉掛け作業」を安全に行うための国家資格です。建設現場や工場など、クレーンを使う作業現場では玉掛けの資格が必須とされています。
玉掛けとは、クレーンのフックに荷物を吊り下げるためのワイヤーロープなどの玉掛け用具を取り付ける作業のこと。荷物の形状や重量に合わせて、適切な吊り具を選定し、荷崩れしないよう確実に取り付ける技術が求められます。
技能講習と特別教育の2種類がある
玉掛けの資格には、つり上げ荷重に応じて「技能講習」と「特別教育」の2種類があります。
・つり上げ荷重1トン以上:玉掛け技能講習の修了が必要
・つり上げ荷重1トン未満:玉掛け特別教育の修了でOK
一般的によく知られているのは1トン以上の「技能講習」の方。本記事でもこちらを中心に解説していきます。
玉掛け技能講習の講習内容と時間数
玉掛け技能講習は、学科講習と実技講習の2部構成。カリキュラムは以下の通りです。
【学科講習】18時間
・クレーンに関する知識:4時間
・クレーンの玉掛けに必要な力学に関する知識:6時間
・クレーンの玉掛けの方法:7時間
・関係法令:1時間
【実技講習】12時間
・クレーンの玉掛け:9時間
・クレーンの運転のための合図:3時間
学科と実技を合わせて30時間、標準では3~4日間の日程で行われるのが一般的です。各講習を修了後に修了試験が実施され、これに合格すれば晴れて玉掛け技能講習修了となります。
気になる玉掛け技能講習の料金相場!都道府県別の比較も
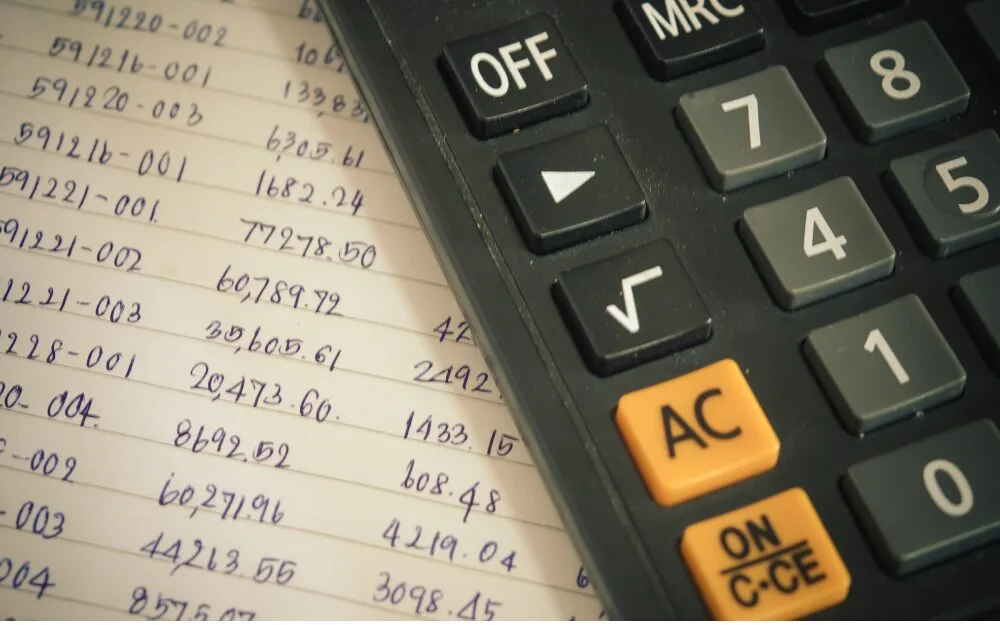
3-4万程度が相場、特別教育なら半分程度
玉掛け技能講習の料金は、講習機関や地域によって異なります。全国平均では、およそ3~4万円程度が相場と言えそうです。
とはいえ、中には2万円台で受講できる地域もあれば、5万円近くかかるところもあるのが実情。各都道府県の労働局のHPなどで、認定講習機関の料金一覧を確認してみるのが確実です。
ちなみに、つり上げ荷重1トン未満の「特別教育」なら、技能講習の半額程度の費用で済むケースが多いようです。
法人申込の方が個人申込より1万円程度安い
企業からの法人申込の場合、料金が割引になる講習機関もあります。個人申込との差額は、1万円程度が一般的なようです。
一方、個人でも複数人数でまとめて申し込めば、団体割引が適用されるケースもあり。申込方法による価格差は、講習機関に直接問い合わせてみると良いでしょう。
ただし、講習料に宿泊費や交通費は含まれていないのが通例。個人申込の場合は、トータルの費用負担を踏まえて講習先を選ぶ必要がありそうです。
割引制度や助成金を活用してお得に受講しよう
料金を少しでも抑えたい方には、各種の割引制度や助成金の活用がおすすめです。
例えば、雇用保険の被保険者なら、「人材開発支援助成金」の対象になることも。条件を満たせば、講習料の最大7割までが助成されます。
他にも、講習機関独自の割引を設けているところもあるので、HPなどの情報をこまめにチェックしてみると良いかもしれません。
受講費用の工面は大変かもしれませんが、料金の相場を押さえつつ賢く制度を利用すれば、お得に資格取得できるはずです。
玉掛け技能講習の所要日数は?スケジュール管理のコツ

学科講習と実技講習の標準的な日数
先述の通り、玉掛け技能講習は学科18時間+実技12時間の計30時間で構成されています。これを標準の日程で消化する場合、以下のようなスケジュールが一般的です。
・【学科講習】2日間(各日9時間)
・【実技講習】1~2日間(1日最大12時間)
学科と実技の間に1日の自由日を設けるケースもあるので、実質3~5日程度の日数は見ておく必要がありそうです。
講習と仕事の両立に必要な休暇の取り方
社会人の方の中には、仕事をしながら玉掛けの資格取得を目指す人も多いはず。講習期間中は、有給休暇を取得するなどして、しっかりと講習に専念できる環境を整えましょう。
ただし、会社によっては連続5日間の休暇取得は難しいかもしれません。そんな時は、講習機関に相談して学科と実技を分けて受講するのも一案です。
「まとめて受講したい」「仕事の都合で分割したい」など、自分のスケジュールに合わせて柔軟に講習プランを組めるところを選ぶのがベターですね。
効率的なスケジュール管理で計画的に資格取得!
玉掛け講習のスケジュールが分かったら、早めに予定を立てて計画的に受講準備を進めましょう。以下のような点を抑えておくと、効率的に資格取得できるはずです。
・授業の予習復習を欠かさず、学科試験に備えた知識の定着を図る
・Web予約などを利用して、講習の空き状況を随時確認する
・上司や同僚にカバーを依頼し、休暇中の仕事のフォロー体制を整えておく
何かとバタバタしがちな日程調整も、早め早めの行動と周到な準備で乗り切れるはず。無理のない講習プランを立てて、資格取得への一歩を踏み出しましょう。
【就職・転職をお考えの方へ】
こんなお悩みありませんか?
- もっと給料を上げたい
- 残業時間が多くて体力的にきつい
- ホワイト企業に転職したい
- もっとプライベートを充実させたい
プロドラ編集部が最もおススメする、ホワイト企業で高年収を目指したい人に”絶対”に利用して欲しいドライバー専門転職サイト!
ドラEVERでしか取り扱いのない好条件の求人が多く、年収アップも目指せます!未経験歓迎の求人も多数あるので、異業種からの転職にもおススメ!
玉掛け技能講習の試験内容を徹底解説!合格のための対策も

学科試験の出題範囲と形式
玉掛け技能講習の学科試験は、4肢択一形式の筆記テストで行われます。出題範囲は以下の通り。
・クレーン等に関する知識
・クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
・クレーン等の玉掛けの方法
・関係法令
学科講習の内容からほぼそのまま出題されるので、しっかりとテキストや配布資料を復習しておけば合格は難しくありません。
模擬問題などもネット上に多数出回っているので、ひと通り解いておくと試験本番に強いでしょう。
実技試験の課題と評価ポイント
実技試験は、実際にクレーンを使用しての玉掛け作業が課題となります。試験時間は30分程度。
評価のポイントは以下の5項目です。
・吊り具の選定
・吊り具の取り付け
・玉掛け作業の手順
・クレーン運転者への合図
・安全への配慮
・日頃の実技講習で手順をしっかり身につけ、安全第一で作業ができれば合格は目前。実技は学科に比べて不合格になるケースも少ないようです。
試験対策に役立つ教材や講習のコツ
とはいえ、試験のプレッシャーに負けて実力を発揮できない受講者も中にはいるもの。
試験対策の定番としては、市販の問題集や参考書に加え、インターネット上の情報を活用するのが有効です。
YouTubeなどの動画サイトには、玉掛け作業の実技映像が数多く投稿されています。プロの技を視聴して手順をイメージトレーニングするのも一案でしょう。
また、技能講習では座学だけでなく実技の反復練習が大切。施設の開放日などを利用して、講師に手取り足取り教わる機会を逃さずに。試験本番までに体で覚えるくらいに実技をマスターしておきたいですね。
玉掛け技能講習の申込方法は?講習までの手続きの流れ

講習実施機関の探し方と選び方のポイント
玉掛け技能講習が受けられる施設は、全国各地の安全衛生技術センターや民間の講習機関など様々。
自分に合った講習先を探すには、以下の観点での比較検討がおすすめです。
・自宅や勤務先からの移動時間と交通の便
・講習スケジュールの確認と日程調整のしやすさ
・受講料の費用感と割引特典の有無
・講師の指導力と施設設備の充実度
・合格実績や口コミ評判
とりわけ、日程と料金のバランスは大切。スケジュール管理と予算面の兼ね合いで、最適な講習先を見極めましょう。
申込みに必要な書類と記入例
講習機関が決まったら、早速申し込みの手続きを。玉掛け技能講習の申込書類は以下の2点が主流です。
【1】受講申込書
受講希望日や氏名、連絡先などを記入します。事前に必ず本人確認書類で内容を確認し、記入漏れがないよう注意。
【2】顔写真
申込書に貼り付けるための、タテ3cm×ヨコ2.4cmの証明写真。無背景で、受験時と同じ姿の写真を用意します。
記入済みの書類は、講習機関の窓口かWebサイトから提出。すると、受講票や案内書などが届くので、内容をよく確認しておきましょう。
講習料の支払い方法と注意点
玉掛け技能講習の料金は、申込時に前払いが原則。支払い方法は講習機関によって異なり、以下のようなパターンがあります。
・現金書留や銀行振込で事前に支払う
・当日の受付時に現金で支払う
・クレジットカードやコンビニ払いに対応
Webサイトでの申込み手続きが主流の昨今、ネット決済のできる講習機関も増えてきました。
とはいえ、受講票が届くまでに料金の入金確認が必要なところがほとんど。支払いの締め切り日には十分注意しましょう。
また、一度納入した講習料は原則として返金不可。体調不良などで受講できなくなった場合のキャンセルポリシーは、事前に必ず確認しておくことをおすすめします。
玉掛け技能講習の合格率は?難易度と合格のコツ

都道府県別の玉掛け技能講習の合格率
玉掛け技能講習の合格率は、おおむね90%以上と高水準。直近の統計では、全国平均で学科95.5%、実技98.8%となっています。
とはいえ、合格率には都道府県ごとにバラつきがあるのも事実。例えば、学科試験の合格率が全国トップクラスなのは秋田県の99.1%。逆に、最下位の青森県は87.7%と、10ポイント以上の開きがあります。
受験対策の程度や試験問題の難易度など、各都道府県の事情が反映された結果と言えそうです。
合格率を上げる学習方法と試験直前の対策
では、講習の合格率を上げるにはどんな工夫が効果的なのでしょうか。ポイントは以下の3つ。
・学科の配布テキストを隅々まで読み込み、重要ポイントを書き出す
・実技は本番さながらの模擬テストを繰り返し、手順を確実に身につける
・試験日程を意識して計画的に勉強し、直前期に知識の総まとめをする
講習中の集中力を高め、効率良く学習を進めることが肝要。最後の追い込みで弱点克服に努めれば、合格への道は大きく近づくはずです。
試験本番に向けては、必要な持ち物の事前チェックを忘れずに。受験票や筆記用具、実技に適した服装など、万全の準備で試験会場に臨みましょう。
万が一不合格でも再試験のチャンスあり!
講習の修了試験は、学科・実技それぞれ1回ずつの受験チャンス。もし不合格でも、一定期間内なら再試験を受けることができます。
おおむね学科不合格の場合は半年以内、実技不合格は1年以内での再チャレンジが可能。ただし、学科と実技の再試験は同日に受けられません。
仮に玉掛け技能講習に落ちてしまっても、希望を捨てる必要はありません。弱点分野を徹底的に復習し、万全の対策で再試験に備えましょう。
難易度は決して低くない玉掛けの試験。でも、あきらめずに合格を勝ち取る粘り強さこそが、プロの玉掛け技能者への第一歩なのかもしれません。
玉掛け技能講習は誰に向いている?おすすめの人の特徴

体力に自信がある人は玉掛けの仕事に適性あり
玉掛け作業には、それなりの体力が求められます。重量物を扱うため、力仕事が多いのが特徴。
例えば、鋼材や鉄筋の束を吊り上げる際は、ワイヤーロープの掛け外しだけでも大変な重労働。現場の作業環境も、炎天下だったり、雨風にさらされたりとハードなことが少なくありません。
力に自信があり、バイタリティ溢れる男性にはうってつけの仕事と言えるでしょう。女性の活躍も目立つ昨今ですが、体力面の適性は高いハードルになりがちです。
安全管理意識の高い人は資格取得後に活躍できる
玉掛けの仕事では、何より安全管理意識の高さが重視されます。ちょっとしたミスが、重大な事故につながりかねないからです。
吊り荷の落下や作業者の挟まれなど、怖い災害事例は枚挙にいとまがありません。危険予知を怠らず、慎重に作業を進められる几帳面さが求められます。
また、クレーン運転士など周囲の作業者とのコミュニケーションも大切。安全最優先の価値観を全員で共有し、息の合ったチームワークを発揮することが理想です。
社会人としての責任感が強く、安全意識の徹底にこだわりを持てる人。そんな資質を併せ持つあなたなら、玉掛けのプロへの適性は十分と言えそうです。
コツコツ努力できる人
忘れてはならないのが、玉掛け技能講習の勉強を地道に続ける忍耐力。座学も実技も、正直に言って覚えることは多岐にわたります。
特に実技試験は、一連の手順を何度も反復練習するしんどさが伴うもの。そこを投げ出さずに励み続けられる持続力が、合格への分かれ道になるはずです。
加えて、現場での経験を積み重ねながら、スキルを向上させ続ける向上心も必要不可欠。失敗を恐れず果敢にチャレンジし、着実にキャリアを積んでいく。
そうしたコツコツ努力を積み重ねられるタイプの人なら、玉掛けの世界で大きく羽ばたけるに違いありません。資格取得もその通過点に過ぎません。
あなたの真摯な努力が、「運ぶ」という崇高な使命を担う原動力になる。玉掛けの仕事は、そんな向上心にあふれる人にこそおすすめしたい職業なのです。
まとめ:玉掛け技能講習は今後の建設業界で必須の資格!

資格取得のメリットを再確認しよう
玉掛け技能講習は、重量物の運搬に欠かせないスペシャリストへの登竜門。資格を取れば、建設現場や工場など活躍の場が大きく広がります。資格手当がつく会社も多く、直接的な収入アップも見込めるでしょう。
何より、手に職をつけることで、ライフステージに合わせて働き方の選択肢が増えるのは大きなメリットです。「モノを運ぶ」という仕事の重要性は、これからも決して色あせません。むしろ、インフラ整備の拡大などを追い風に、玉掛け技能者の需要はさらに高まると予想されます。
まだ資格を持っていないなら、今すぐ取得に動き出すべき。最初の一歩を踏み出せば、新たなキャリアへの扉が必ず開かれるはずです。
計画的に講習を受けて効率良く合格を目指そう
玉掛け技能講習を効率良く修了するには、万全の受講プランが肝心。日程と予算、通いやすさなどを考慮して、最適な講習先を選びましょう。加えて、今回解説した試験傾向を踏まえた対策も怠らないこと。学科の幅広い知識と、実技の確実な手順を、コツコツ身につけることが合格への近道です。
周到な準備と地道な努力さえ積み重ねれば、きっと良い結果がついてくるはず。資格取得のために費やした労力は、必ず仕事の質を高めるための糧になってくれるでしょう。
資格を活かせる仕事に就いてスキルアップを図ろう
玉掛けの資格を手に入れたら、次はその力を存分に発揮できる職場を選ぶ段階。資格を活かせるやりがいのある環境で、ステップアップを目指しましょう。経験を重ねるごとに、玉掛けのスペシャリストとしての腕に磨きがかかります。ゆくゆくは、現場の安全管理をまとめる立場になれるかもしれません。
さらに、クレーン運転士など関連資格の取得を目指すのもおすすめ。玉掛けとの相乗効果で、資格の価値をより一層高められるでしょう。プロとしてのプライドを胸に、存在感を発揮し続けること。それが、建設業界に欠かせない即戦力となるのです。
有資格者だからこそ担える、「運ぶ」という重責。その使命を胸に、資格取得という新たな一歩を踏み出してみませんか。
玉掛け技能講習は、建設業界の未来を切り拓く、エキスパートへの第一歩。ものづくり日本の礎を支える仕事に、あなたの力を貸してください。
資格取得を通じて、現場の安全と効率アップの両立に貢献できる。そんな玉掛けのプロフェッショナルとして、ぜひ活躍されることを期待しています。
こんなお悩みはありませんか?
- 「年収を上げたい…」
- 「ホワイトな職場に転職したい…」
- 「未経験だけどドライバーになりたい…」
近年、日本ではドライバーの数が減少傾向にあるため、今の職場よりも良い給与や環境で働ける企業から内定を獲得できる可能性が高まっているのです。
今よりもいい会社で働きたい方は「ドラEVER」で探してみませんか?
地域や職種、給与、エリア等のあなたのご希望をお聞かせください。あなたのキャリアを全力サポートします。
 プロドラ|プロドライバーのための情報サイト
プロドラ|プロドライバーのための情報サイト